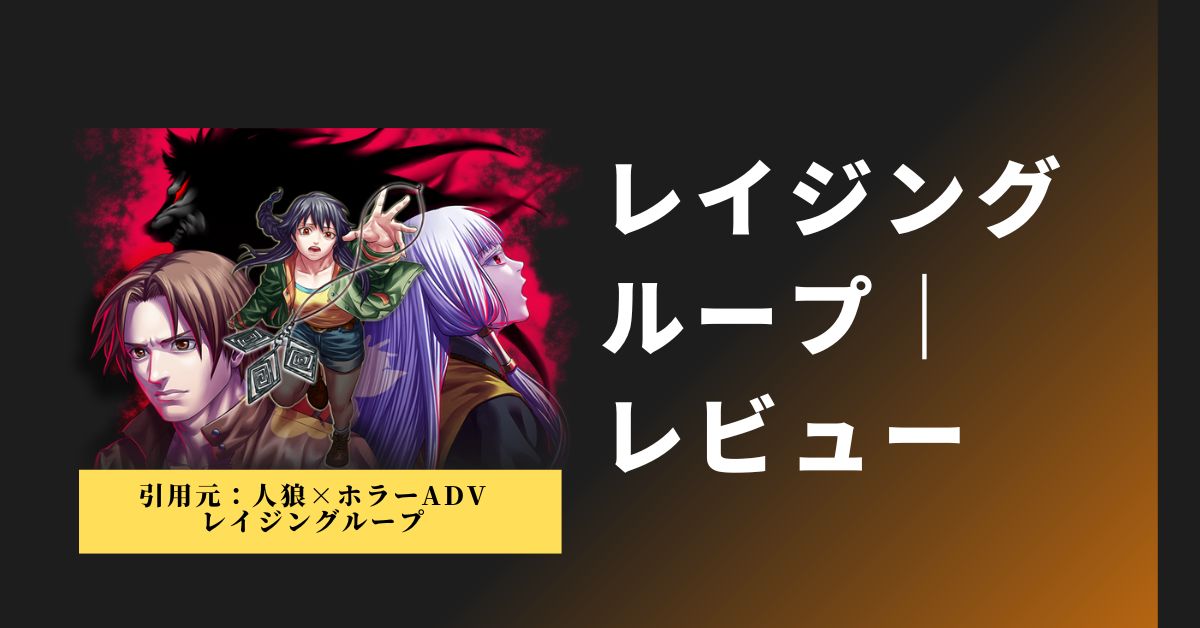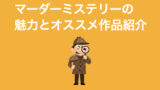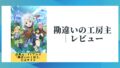こんにちは、アシカです!
今回は、ノベルゲーム好きなら一度は耳にしたことがあるであろう、和風サスペンスADV『レイジングループ』をレビューします。
人狼ゲームとループものを組み合わせた本作は、「選択肢を選んで進める」シンプルな仕組みでありながら、緻密なシナリオと独自システムによって、プレイヤーを徹夜必至の没入体験へと導いてくれます。
ゲームの評価基準について
ゲームの評価については、下記のランクごとに分けております。
あくまで、私自身のプレイ体験をもとにした評価ですので、購入の参考程度に考えていただけると幸いです。
▪️Sランク・・・神作。ゲーム好きであれば必ずプレイしてほしい作品。
▪️Aランク・・・名作。一人によってはSランクになってもおかしくない作品。
▪️Bランク・・・普通に面白く、フルプライスで購入しても満足する作品。
▪️Cランク・・・凡作。
▪️ランク外・・・自分には合わなかった作品。
『レイジングループ』とは?
『レイジングループ』は、2015年にスマートフォン向けに配信され、その後PS4・PSVita・Nintendo Switch・PCなどでも発売されたサスペンス・ホラーアドベンチャーゲームです。
人狼ゲームを題材にした心理戦と、ループ構造を取り入れた独特の仕掛けで、多くのプレイヤーを虜にしました。
私が初めてプレイしたのはSwitch版でした。
「ノベルゲーム=恋愛中心」というイメージを持っていたのですが、本作を通してその考えは大きく覆されました。
次に何が起こるのか分からない緊張感や、キャラクターたちの駆け引きに引き込まれ、一度始めたら止まらなくなるほど夢中になりました。
舞台となるのは、山奥にひっそりと存在する村。
そこでは古くから伝わる儀式が行われ、参加者は互いに疑い合いながら「生き残り」をかけて夜を過ごすことになります。
閉ざされた空間で繰り広げられる心理戦と、人間の裏表があらわになるドラマが、本作の大きな見どころです。
『レイジングループ』総合評価
| ストーリー | |
| ゲームシステム | |
| ジャンル | サスペンス・ホラーADV |
| 対応機種 | Switch / PS4 / PSVita / PC / スマートフォン |
| 発売元 | ケムコ |
| 公式サイト | レイジングループ 公式サイト |
| クリア時間 | 25時間 |
今回は、総合評価Sランクとさせていただきます!
『レイジングループ』は、村を舞台にした閉鎖的な人狼サスペンスという強烈な題材を、見事にゲームとして昇華した傑作です。
特に「ループ」という仕掛けを物語に組み込むことで、ただの読み物ではなく、プレイヤー自身が推理と選択を重ねながら物語を体験できる点が素晴らしいと感じました。
キャラクター同士の心理戦や、緊張感のある駆け引きは一度始めると止まらなくなる中毒性があります。
また、テキストのテンポが良く、ホラー要素だけでなく時折差し込まれるコメディや人間ドラマが作品全体のバランスを保っています。
ボリューム的にも非常に満足度が高く、物語を進めていくことで見えてくる真実や仕掛けが、プレイヤーにさらなる驚きを与えてくれます。
価格以上の体験を提供してくれる作品と言って間違いありません。
正直なところ、人を選ぶ題材ではありますが、刺さる人には間違いなく忘れられない一本になるはずです。
ミステリーや人狼系の作品が好きな方には、全力でおすすめできるタイトルです。
『レイジングループ』関連作品
もし「ゲームはあまりやらないけど物語には興味がある」という方には、小説版『レイジングループ』が断然オススメです。
ゲーム版の緊張感あふれるストーリーをそのまま小説として楽しめるため、コントローラー操作や長時間のプレイが苦手な人でも気軽に作品世界に浸れます。
しかも小説版ならではの細かな心理描写や地の文の解説によって、登場人物たちの心の動きがより鮮明に伝わり、物語の奥行きを深く味わえるのが魅力です。
ゲーム版で体験できるドキドキや驚きが文字の力で再現されているので、「読むだけであの恐怖と興奮を追体験できる」と言っても過言ではありません。
また、小説版は全7巻で完結しており、長すぎず短すぎない絶妙なボリュームとなっています。
さらに、『レイジングループ』の世界をより深く理解したい方には、公式解説本もぜひ手に取っていただきたい一冊です。
各キャラクターの心理や裏設定、ストーリーの仕掛けを徹底的に掘り下げており、「そういう意図があったのか!」と驚かされること間違いなし。
小説やゲームを読み終わった後に解説本を開けば、作品全体の完成度の高さに改めて感嘆させられるはずです。
小説版と解説本をあわせて楽しむことで、『レイジングループ』という作品の魅力を余すことなく堪能できます。
良かった点
①「死に戻り」とロック付き選択肢が生み出す中毒性
『レイジングループ』を一言で表すなら「やめ時を完全に見失うノベルゲーム」です。
その理由は、物語の仕組みに組み込まれた「死に戻り」と「ロック付き選択肢」のシステムにあります。
主人公は、ただ死ぬだけで終わりません。
むしろ「死ぬこと」こそが次の真実に進むための唯一の手段になっています。
ゲームを進めていくと、選択肢の中には鍵がかかっていて読めないものが多数出てきます。
しかし主人公が死ぬと、その死が「鍵」となり、これまで閉ざされていたロック付きの選択肢を解放できるのです。
つまり、ただ正解を選んで生き延びるのではなく、あえて死ぬことを繰り返してルートを広げていく必要がある。
この「死ぬことが前進になる」という逆転の発想が、プレイヤーを否応なしにのめり込ませます。
特に印象的なのは、システム側から「この選択肢は当分解放できないから気にしないでね」とわざわざ注意される場面。
そんなことを言われたら、むしろ気になって仕方がないじゃないですか笑
プレイヤーは「早くその選択肢を開きたい!」という欲望に駆られ、ストーリーを進めるモチベーションがどんどん高まっていきます。
私自身、何度も「これで最後にしよう」と思いながら、深夜までプレイを続けてしまいました。
仕事がある平日に手を出したらアウト。
気づけば「あと一つ鍵を開けたら寝よう」が「次の死に戻りだけ見てから」に変わり、朝方までやめられなくなる危険性があります。
なので長期連休や金曜の夜に一気にプレイするのがオススメです!
気づけば時間を忘れて、夢中で鍵を集め続けている自分に驚くはずです。
この「死に戻り」と「鍵」の仕組みは、ただの演出ではなくプレイヤー心理を徹底的に突いたゲームデザインです。
死ぬことが絶望ではなく、新しい知識と展開を得る希望に変わる。
選択肢の一つひとつに意味が宿り、解放された瞬間の快感が次の中毒へと繋がっていく。
物語を読み進める面白さと、ゲームとしての挑戦心が完璧に融合しているからこそ、プレイヤーは「もう一度だけ」と言いながらやめられなくなるのです。
②ホラー×人狼×ミステリーの三重奏
『レイジングループ』の魅力はなんと言っても「ジャンルを超えた緊張感の連鎖」にあります。
序盤を彩るのは、人狼ゲームを軸にしたサバイバル的なスリル。
しかし、ただの推理合戦で終わらないのがこの作品の恐ろしいところです。
最初は「人狼を見つけて排除できればクリアなんでしょ?」と軽く構えていたのに、物語が進むにつれ、その期待は裏切られます。
村のしきたりや古くからの因習が複雑に絡み合い、さらに登場人物たちの思惑や隠された事情が積み重なっていくことで、シンプルな人狼ゲームがいつしかとんでもなく歪んだ舞台へと変貌していくのです。
その展開はまさにホラー×人狼×ミステリーの三重奏。
村という閉鎖空間が持つ不気味さと、人狼ゲーム特有の心理戦のスリル、そして「この状況に必ず裏がある」というミステリー的な疑念が、同時にプレイヤーを追い詰めてきます。
誰を信じるべきか? なぜこの儀式が続いているのか? 表では笑顔を見せる人間たちの裏に隠された本音は? 真相に近づこうとするほど、疑念と緊張は増していきます。
そして、プレイヤーを徹底的に引き込むのが無理ゲー感です。
どんなに頑張っても解決の糸口が見いだせない展開の連続のため「これ、どう転んでも絶望じゃないか?」と心が折れそうになる瞬間が何度も訪れます。
けれど、その不可能に見える状況だからこそ、主人公と一緒になって「打開の一手はどこにあるのか」と食らいついてしまう。読んでいて胃が痛くなるような緊張感すら、逆に快感へと変わります。
ホラー的な恐怖で心拍数を上げられ、人狼ゲーム的な疑心暗鬼で神経をすり減らし、ミステリー的な謎解きで知的好奇心を刺激される。
三つのジャンルの旨味が同時に押し寄せる体験は、ほかのノベルゲームではなかなか味わえません。
「怖い」「苦しい」「でも続きが気になる」――そんな矛盾した感情に振り回されながら、プレイヤーは最後まで物語から目を離せなくなるはずです。
③伏線の巧妙さと知的バトルの応酬
『レイジングループ』を語る上で外せないのが、徹底的に計算された伏線の張り方です。
一見すると何気ない一文、登場人物のふとした仕草や会話――そうした「ただの演出」と思える細部が、後になって「え、これ伏線だったの!?」とひっくり返される。
その瞬間の快感は、まるで上質な推理小説を読み込んでいる時のような充実感があります。読み返すと「あの時点でここまで仕込まれていたのか」と気づける作り込みの深さに、感心せずにはいられません。
そして、その伏線を活かす舞台となるのが心理戦です。
主人公は非常に頭の切れる青年で、常に周囲を疑い、冷静に状況を分析しています。
普通のノベルゲームの主人公であれば流されてしまうような局面でも、彼は徹底的に警戒し、思考を巡らせる。
その姿勢がプレイヤーに安心感を与えると同時に、「この先にどんな読み合いが待っているのか」と期待を煽ってきます。
ただし、彼が優秀だからといって物語が楽勝になるわけではありません。
人狼ゲームのループごとに参加者が変化し、その中には主人公に匹敵する、あるいはそれ以上の知略を持つ人物が登場します。
彼らの策略は一筋縄ではいかず、正面から戦えば一瞬で形勢が逆転してしまうことも。
毎回のやり取りが知恵と心理をぶつけ合う真剣勝負であり、読んでいるこちらまで手に汗握らされます。
さらに面白いのは、この知的バトルが「人狼ゲームの勝敗」という範囲にとどまらない点です。
誰を信じ、誰を疑い、どのように立ち回るか――そのすべてが、村の因習や登場人物たちの思惑と密接に結びついています。
単なる推理や論理戦ではなく、人間同士の信頼や裏切り、恐怖や欲望までもが絡み合うため、勝ち筋は一層見えづらくなる。だからこそ、勝利を手にしたときの快感は格別です。
『レイジングループ』の真骨頂は、この伏線の巧妙さと知的バトルの熾烈さが完璧に噛み合っている点にあります。
じわじわと効いてくる布石が、頭脳戦の中で鮮やかに回収される。その瞬間の爽快感を味わいたいなら、このゲームは間違いなくプレイする価値があります。
④クリア後も楽しめる追加要素
『レイジングループ』は本編をクリアした時点でも十分に満足度の高いゲームですが、Switch版ではさらにその先が用意されています。
それが「主人公以外の視点から物語を覗ける追加要素」です。
これが本当に面白い! 本編を進めているとき、「このキャラは今、裏で何を考えていたんだろう?」と気になる場面が必ず出てきます。
人狼ゲームという性質上、登場人物たちは誰もが何かを隠しており、時に味方のように振る舞いながらも、実は別の目的を抱えていたりする。
その裏側を知れることで、プレイ中に感じていた「違和感」や「疑問」が一気に解消されていきます。
特に印象的だったのは、クリア後に「あの時この人、そんなことを考えていたのか!」と驚かされる瞬間の多さ。
本編で見てきた人間関係や駆け引きが、全く違う角度から鮮明に浮かび上がり、キャラクターの評価がガラリと変わってしまうこともあります。
中には「敵だと思っていたキャラに、実はこんな背景があったのか」と胸が熱くなることもあれば、「信じていたのに…」と再び裏切られた気持ちになることも。
これによって、物語が単なる一周限りの体験ではなく、何層にも重なったドラマとして感じられるのです。
しかも、この追加要素は単なるおまけにとどまらず、作品全体の完成度をさらに高めています。
クリア後に新たな情報を得ることで、本編をもう一度振り返りたくなりますし、知っている展開を違う目線で追うことで、まったく新しい発見がある。
二周目以降も楽しめる作りになっているので、「まだ遊べるのか!」という嬉しい驚きがありました。
他のノベルゲームだと、エンディングを迎えたら物語は終わりという作品も多いですが、『レイジングループ』はそこからもう一段階プレイヤーを楽しませてくれる。
エンディングを見て満足するどころか、「クリアしたはずなのに、まだこんなに面白い」と感じられるのは、このゲームならではの大きな魅力です。
気になった点
『レイジングループ』は完成度が非常に高いノベルゲームですが、個人的に気になるところもありましたの、順番に語っていきます。
まず挙げたいのが、序盤のホラー要素です。
雰囲気づくりが本当に上手く、私は正直一人でお風呂に入るのも怖いほどビビらされました。
人狼ゲームの緊張感と相まって、夜に一人でプレイしていると背後が気になって仕方なくなるレベルです。ホラーが苦手な方には、少しハードルが高く感じられるかもしれません。
また、後半に進むと一気に事件解決モードに切り替わり、心理戦や謎解きの緊迫感が前面に出てきます。
ジャンルが段階的に変化するため飽きずに楽しめる一方、「怖いノベルゲームを最後まで期待していた」という方には、後半の雰囲気がガラッと変わる点が好みを分けるかもしれません。
さらに注意してほしいのは、とんでもなくびっくりするシーンがあること。
油断していると本気で飛び上がるほどなので、ホラー耐性が低い方は心してプレイすることをおすすめします笑
ただ、これらの点は裏を返せば「ホラー・ミステリー・推理」と複数のジャンルを一作で体験できる魅力でもあります。怖さと知的な緊張感のバランスをどう受け止めるかで評価が変わる部分と言えるでしょう。
人狼ゲームが題材のオススメ作品
『レイジングループ』を楽しんだ方には、同じく「人狼ゲーム」をモチーフにした作品にもぜひ触れてほしいです。
推理と心理戦のスリルはもちろん、作品ごとにアプローチが大きく異なるので、新鮮な驚きが味わえます。
①グノーシア
『レイジングループ』で「死に戻り」と人狼ゲームが生み出す中毒的な物語体験に心を掴まれた人にこそプレイしてほしいのが、『グノーシア』です。
人狼ゲームを題材としながら、その舞台は宇宙船。プレイヤーは毎回異なる役職を与えられ、AIキャラクターたちと疑心暗鬼の議論を繰り返すことになります。
特筆すべきは、AIでありながらキャラクターたちが驚くほど自律的に動き、まるで本当に人間同士で人狼をしているかのようなリアルな駆け引きが展開されること。
毎回のループで役職や配役が変わり、議論の流れも異なるため、同じ展開は二度と訪れません。
『レイジングループ』が緻密なストーリーで魅せるなら、『グノーシア』は「プレイヤー自身が人狼に挑み続ける」体験そのものが物語になります。
勝ち負けだけでなく、仲間を信じるか裏切るか、その選択一つひとつがドラマを生み出していくのです。
そして最後に待っているのは、このループの謎そのものへの解答。
なぜ繰り返すのか? グノーシアとは何者なのか?
推理と心理戦を重ねた先に明かされる真実は、『レイジングループ』で心を揺さぶられた人の胸にも必ず響くはずです。
②生きたがりの人狼
『レイジングループ』で「死に戻り」と人狼ゲームが生み出す緊張感あふれる物語体験に心を掴まれた人にこそ読んでほしいのが、『生きたがりの人狼』です。
本作は、人を喰って姿と記憶を奪い、なり替わる化け物「人狼」が人間社会に紛れ込む世界を舞台に、異常な生への執着を持つ青年・灰堂ヒロナリの運命を描いています。
人狼が誰なのか、そしていつ襲われるのかという緊張感が常に張り詰めており、ページをめくる手が止まらなくなる作品です。
特筆すべきは、人狼や仲間たちの心理描写の巧みさです。
ヒロナリや幼馴染のコウキといったキャラクターたちは、それぞれが複雑な思惑を持ち行動するため、読者は常に「次に何が起こるのか」を予測しながら読み進めることになります。
また、ヒロナリの生きるための判断や行動の一つひとつが、物語に緊迫感と予測不能なドラマを生み出しています。
『レイジングループ』がループを通じて真相を解き明かす物語の巧妙さで魅せるなら、『生きたがりの人狼』は「生き残るために駆け引きを続ける」体験そのものが読者を惹きつけます。
誰を信じ、誰を警戒するのか、その選択が物語を大きく動かすため、最後まで目が離せません。
そして明かされるのは、人狼の正体やヒロナリの運命、そして彼らが置かれた状況の真相。予想外の展開と心理戦の連続は、『レイジングループ』で心を揺さぶられた人の胸にも必ず響くはずです。
『生きたがりの人狼』について、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
人狼ゲームが好きなら次はマーダーミステリーに挑戦!
『レイジングループ』で味わった、人狼ゲームの緊張感や心理戦のスリルに夢中になった方には、マーダーミステリー(通称:マダミス)もぜひオススメです。
マダミスとは、参加者が登場人物の役割を演じながら、誰が犯人かを推理していくテーブル型の推理ゲーム。
登場人物の秘密や思惑を読み解きながら物語を進めるため、一瞬たりとも気が抜けません。
人狼ゲームと同じく、他者の言動や心理を考慮しつつ推理を進める面白さがあり、まさに『レイジングループ』の体験をテーブル上で楽しむ感覚です。
これまで私がプレイしたマダミス作品のレビュー記事もまとめているので、次に挑戦する作品選びの参考にどうぞ。謎解きと心理戦の連続に、あなたもきっと夢中になります。
これぞ人狼×ループの傑作――『レイジングループ』総括
『レイジングループ』は、単なるノベルゲームの枠を超えた、人狼ゲームとループものを掛け合わせた圧倒的中毒性を誇る作品です。
主人公の「死に戻り」を軸に、鍵付き選択肢や緻密な伏線、心理戦が絶妙に絡み合い、プレイヤーは常に緊張感と興奮の中で物語を進めることができます。
前半のホラー&サイコ要素で心臓が飛び出るかと思えば、後半は事件解決の推理劇に没入できる二段構えのストーリー構成も見事で、最後まで目が離せません。
さらにSwitch版では、クリア後に主人公以外の視点で物語を追体験できる追加要素もあり、何度でも楽しめるのも大きな魅力です。
人狼ゲームや心理戦、緻密なミステリーが好きな方はもちろん、これまでノベルゲームにあまり触れたことがない方でも、その独自のシステムと物語の引き込み力に驚くはずです。7巻で完結する書籍版もあり、ゲームがなくても物語を存分に楽しむことができます。
総合評価はSランク。心の底から物語に没入し、緊張感と感動を同時に味わえる、間違いなくおすすめできる一作です。